飼い主の亡き後のペットのために
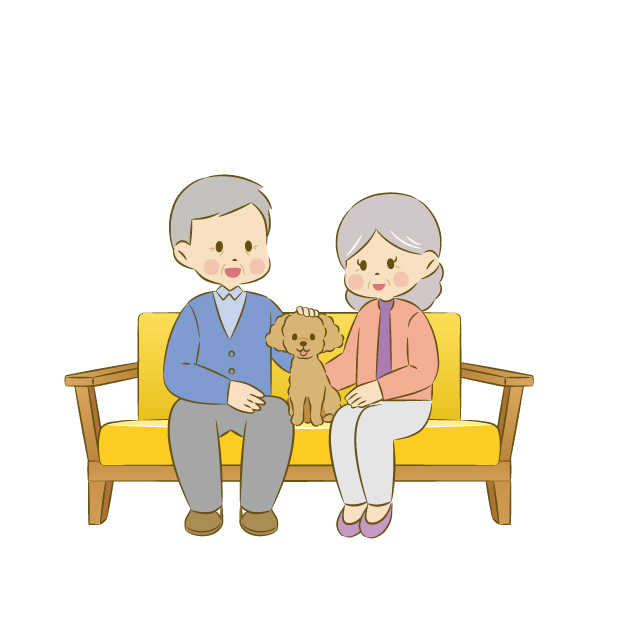
高齢化社会の進行に伴い、飼い主がペットより先に亡くなってしまうケースが今後も増えていくことが予想されます。ここではそのような場合にそなえ、ペットの将来を考えてどのようなことができるのかをまとめてみました。
負担付遺贈
負担付遺贈とは、遺贈をするにあたって、法律上の一定の義務を受遺者へ負わせることをいいます(民法1002条)。負担付遺贈では、財産を遺贈する代わりに、特定の誰かを世話(扶養)する義務を負わせたり、ペットの飼育を負担させることも可能です。信頼できる人に飼育を託し、その対価として財産を遺すことで、飼い主亡き後のペットの生活を守ることができます。
負担付遺贈の仕組みは以下のとおりです。
- 遺言書に記載 「第〇条 ○○氏(住所東京都〇〇区○○1丁目2番地、生年月日平成10年1月1日生)に現金100万円を遺贈する。この贈与は、遺言者の所有する愛犬ポチ(柴犬、10歳、オス、茶色)の世話をポチの生涯にわたって行うことを条件とする。ただし、遺言者よりも先に愛犬ポチが死亡した場合は、上記の現金は遺贈しない。」といった形で記載します。
- 受遺者(財産を受け取る人)はペットの飼育という「負担」を引き受ける代わりに財産を受け取ります。(しかし、遺贈は一方的な意思表示であるため受遺者は遺贈を放棄することができ、その場合はペットの飼育義務も生じません。従って、ペットにとって不安定な状態に陥る可能性もあります。)
- 遺言執行者を選任し、飼育状況の監視や改善要求が可能です。
負担付死因贈与契約
ペットの飼育に関する負担付死因贈与契約とは、飼い主が亡くなった後にペットの世話をしてもらうことを条件に、財産を譲る契約です。これは生前に双方の合意で結ばれる契約であり、遺言よりも履行の確実性が高いとされています。
契約の仕組みと特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約当事者 | 飼い主(贈与者)と新しい飼育者(受贈者) |
| 贈与のタイミング | 飼い主の死亡時に効力が発生 |
| 条件 | ペットの終生飼育などの義務を負う |
| 契約形式 | 書面での契約が推奨、公正証書にすることも可能 |
| 執行者の指定 | 契約履行を監督する第三者を設定できる |
メリットとしては、履行の確実性が高い(遺言と違い、契約なので合意すれば原則として一方的な拒否ができません)、飼育方法を細かく指定できる(別紙で「飼育指示書」を添付することで、希望通りの飼育が可能)、執行者による監督が可能(飼育状況に問題があれば改善請求や契約解除も可能)などがあげられます。
負担付死因契約書の記載例(抜粋)
第1条(贈与) 甲は、乙に、現金100万円を贈与することを約し、甲の死亡により効力を生ずる。
第2条(負担義務) 乙は甲の死亡後、甲の飼育していた愛犬ポチ(柴犬、10歳、オス、茶色)を終生にわたり飼育する義務を負う。 飼育方法は別紙「飼育指示書」に従うものとする。なお、乙が甲よりも先に死亡した場合は本契約は効力を失う。
第3条(執行者) 本契約の執行者は丙(住所東京都〇〇市〇〇町3丁目4番地、生年月日昭和50年2月2日)とする。
ペット信託
ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、病気や高齢でペットの世話ができなくなった場合に備えて、ペットの飼育費用を信頼できる第三者に託し、ペットの生涯を守る仕組みです。飼い主の高齢化や認知症、老人ホーム入所などで飼育できない状態に備え、ペットの生活を守る手段とされています。
ペット信託の構成
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 委託者 | 飼い主(信託契約を結ぶ人) |
| 受託者 | 飼育費を管理し、飼育者に支払う人(個人・団体) |
| 受益者 | ペットの飼育者または施設 |
| 信託監督人(任意) | 飼育状況を監督する第三者 |
- 飼い主が信託契約を結び、飼育費を信託口座に預けます。
- 万が一の事態(死亡・入院など)が起きたら、預けられた飼育費を受託者が飼育者に支払います。
- ペットは新しい飼育者のもとで飼育されます。
- 必要に応じて、信託監督人が飼育状況をチェックします。
- ペットが亡くなることにより信託を終了させますが、信託財産の枯渇によっても終了することになるため注意が必要です。
メリットとしては、飼育費が相続財産と別管理されるため、確実にペットのために使われる、飼い主の病気や認知症など生前のリスクにも対応可能であることなどがあげられます。
注意点としては、飼育者の選定には信頼関係が重要であること、飼育費の目安はペットの種類・年齢によって異なるので十分な見込み額を算定することなどです。
死後事務委任を活用する
死後事務委任契約とは、委任者が亡くなった後に生ずる様々な事務(死後事務)について処理する権限を受任者に付与する契約です。一般的には行政に対する死亡の届け出、葬儀、埋葬、供養に関すること、社会保険、契約関係の整理、遺品や家財の整理などを行いますが、ペットの飼育や譲渡を個別に委任することも可能です。
死後事務委任契約にペットの世話を含める場合、以下について定めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委任者 | 飼い主(契約を依頼する人) |
| 受任者 | ペットの世話を引き受ける人(親族・友人・業者など) |
| 契約内容 | ペットの引き取り、飼育、譲渡、通院、費用管理など |
| 契約形式 | 書面で作成、公正証書にすることで法的効力が強まる |
実際の手順としては、
飼育者の指定 信頼できる人や団体を事前に選定し、契約書に明記します。受任者が飼育できなくなることも考慮してペットシッター専門の業者や保護団体との事前合意も必要です。
飼育費用の準備 飼育に必要な費用を預託します。ペットの種類や年齢などにより準備する金額をあらかじめ算定する必要があります。そして契約書には「飼育費として○○万円を支払う」と記載します。
飼育指示書の添付 ペットの性格、食事、通院、好きな遊びなどを記録して添付します。
譲渡先の指定 新しい飼い主や施設を事前に決めておきます。保護団体や老犬ホームなども選択肢になります。
死後におけるペットの飼育事務の委任契約記載例
第○条(ペット飼育の委任)
甲(委任者)は、甲の死亡後における甲の愛犬「ポチ」(柴犬、10歳、オス、茶色)の飼育を乙(受任者)に委任し、乙はこれを受任する。
2.乙は、甲の愛犬「ポチ」をその生涯にわたり適切に飼育する。
第○条(飼育費用の預託)
甲は、愛犬ポチの飼育費用として、本契約締結時に現金100万円を乙に預託する。乙はこれを受領し、愛犬ポチの飼育目的のみに使用することを約す。
2.乙は、飼育費用の使用状況、愛犬ポチの健康状態など生活状況を適宜記録し、甲の相続人その他利害関係人から請求があった場合に報告する義務を負う。また、愛犬ポチが病気、怪我等により健康状態が悪化した場合には、乙は甲の相続人にその旨を直ちに報告し、必要な対応について協議し対応する。
3.乙が甲の愛犬の飼育に要した実費(医療費・食費等)は本条第1項に定めた預託金から支払う。なお、預託金が不足する場合には、甲の相続人に対しこれを請求することができる。
第○条(報酬)
甲は、本契約の報酬として、現金50万円を乙に支払い、乙はこれを受領する。
以上、飼い主が亡き後、事情により飼育ができなくなった場合の対応についてまとめましたのでご参考にしてください。
負担付遺贈、負担付死因贈与、ペット信託、死後事務委任契約などについて、まずは行政書士などの専門家にに相談していただければと思います。
お気軽にお問い合わせください。070-9044-9871受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください