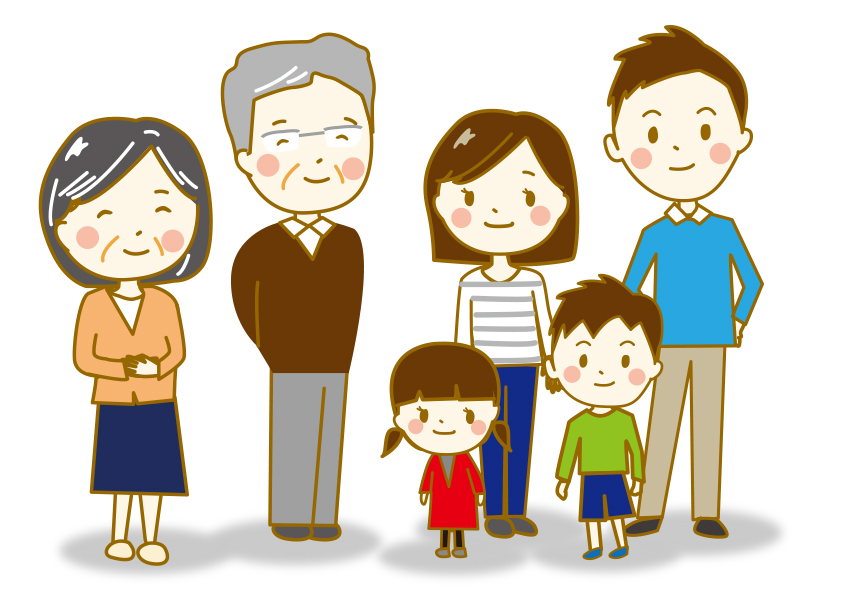みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
住民票や戸籍を取り扱う業務で質問されることですが、世帯主と戸籍の筆頭者とはどのように違うのでしょうか。整理してました。
世帯主とは
法律上で「世帯主」は、明確な定義が存在しないようです。ただし、住民基本台帳法や各種行政制度の中で、形式的・実務的に記載があります。
- 住民基本台帳法第7条第4号により、住民票には「世帯主」または「世帯主との続柄」を記載することが定められています。
- 厚労省の通知より「「世帯主」とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者」(厚生労働省)をいう。」とされています。
つまり、「世帯主」は法律上の資格ではなく、住民票上の代表者として扱われる存在です。
世帯主になれる人
年齢制限があり、15歳未満は世帯主になれません。性別・収入は関係なく、夫婦どちらでも世帯主になることは可能です。一人暮らしの場合は自動的に本人が世帯主になります。
世帯主の役割
世帯主の役割としては、行政手続きの代表者となる、国民健康保険や年金などの納付義務が世帯主に課される、給付金や行政通知が世帯主宛に届くなどです。
世帯主の変更は可能
住民票上の世帯主は、行政手続きの代表者として扱われますが、家族構成や生活状況の変化に応じて変更できます。
- 親から子へ変更(親が高齢になった場合など)
- 夫婦間で変更(妻が世帯主になるなど)
- 世帯主が死亡した場合など
世帯主が死亡した場合など世帯主を変更するには「世帯変更届」を市区町村役場に変更から14日以内に提出する必要があります。
戸籍の筆頭者とは
戸籍の最初に記載される人物です。戸籍の「見出し」として機能します。例えば、婚姻届けを提出すると、新たに戸籍がつくられます。その戸籍の一番最初に記載されている人が筆頭者です。
ただし、法的な権限や特別な地位があるわけではありません。その戸籍(家族)を代表しているとか、その戸籍の管理をしているとか、そのような法的な権限などはありません。
戸籍の筆頭者になる方法
戸籍の筆頭者になるには、新しい戸籍を作成する際に決める方法によります。
- 結婚による新戸籍編成:結婚すると、夫婦の戸籍が新たに作られます。その際に、夫婦の氏を変更しない人が戸籍の筆頭者になります。例えば、妻が夫の氏に変更した場合は、夫が戸籍の筆頭者です。
- 離婚による新戸籍編成:離婚した場合は筆頭者でないものは夫婦の戸籍から除籍されます。除籍された後、婚姻前の戸籍に戻らず新戸籍を作成することもできます。その場合には、新戸籍で筆頭者となります。
- 分籍による新戸籍編成:親の戸籍から抜け、自分だけの戸籍を作ることです。15歳以上であれば分籍が可能で、自分だけの戸籍を作ることができ、その場合は自分が戸籍の筆頭者になります。
- 転籍で本籍地を変更:本籍地を変更して新しい戸籍を作る際にも、筆頭者が新たに設定されます。
戸籍の筆頭者の役割
戸籍の筆頭者には、法的な「役割」や「権限」はありません。戸籍を識別するための見出しのような存在です。
戸籍の筆頭者は変更できない
戸籍の筆頭者が死亡した場合、他の家族がその戸籍に残っていても、筆頭者は変更されません。亡くなった筆頭者は戸籍の中で「死亡」と記載されますが、筆頭者の位置はそのままです。
世帯主と戸籍の筆頭者の違いまとめ
| 項目 | 世帯主 | 戸籍の筆頭者 |
| 管轄制度・法 | 住民基本台帳制度 | 戸籍法 |
| 記載書類 | 住民票 | 戸籍 |
| 変更の可否 | 変更可能 | 変更不可 |
| 役割 | 世帯を代表する者、行政手続きの対象者 | 戸籍の識別、見出し |
| 記載されている人 | 世帯主と同じ住所に住民登録している同居人 | 戸籍法上の家族 |
それぞれの制度の目的、趣旨を理解しておくことが大切かと思います。