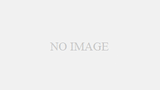みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
子のないご夫婦の相続対策としては「遺言書」の作成があげられます。遺言書をつくっておくことで、兄弟に財産がとられることなく配偶者だけに財産を相続させることもできます。このほかにも、養子縁組をし、養子をとることでも相続財産の分散を防ぐことができます。
養子縁組すると
養子縁組をすると、養子と養親の間に法定血族関係が生じます。養子は養親の子となりますので、第1順位の法定相続人となります。従って、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹は相続権を失うことになります。
その他にも以下のメリットがあります。
- 養子は法定相続人として扱われるため、相続税の基礎控除額が増加します。(例:基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)
- 養子になった姪は相続税の2割加算対象外になります(通常、甥姪は加算対象)。
- 養子になると、姪にも子としての遺留分(最低限の相続分)が認められます。
結婚している姪っ子も養子にすることができるのか
もちろん、結婚している者を養子にすることは可能です。結婚している一方を養子にすることもできますし、夫婦を養子とすることもできます(夫婦養子)。
但し、結婚している一方のみを養子とする場合には、その配偶者の同意が必要とされています(但し、その配偶者が意思表示できない場合(重度の認知症など)には、例外的に単独で養子縁組が可能です)。
養子となる姪っ子の「姓」は
では、養子になった場合の養子の姓(氏)はどうなるのでしょうか。
民法第810条において養子は養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。と定められています。
以下にケースごとの姓の扱いをまとめると
| 状況 | 養子本人の姓 | 配偶者の姓 |
|---|---|---|
| 養子が婚姻前に養子縁組 | 養親の姓に変更 | 該当なし |
| 養子が婚姻後に養子縁組し、婚姻時に自分の姓を選択 | 養親の姓に変更 | 配偶者も養親の姓に変更される |
| 養子が婚姻時に配偶者の姓を選択していた | 養親の姓には変更されない | 配偶者の姓のまま維持される |
このように、姪を養子にすることは相続対策として有効ですが、親族間の信頼関係や将来の相続財産の使われ方も含めて慎重に検討することが大切です。