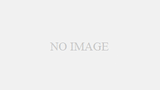相続人の調査
相続が開始した場合、遺言書を確認することと併せて法定相続人を特定します。法定相続人の特定には、故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得し、配偶者、直系卑属(子)、直系尊属(親)、傍系血族(兄弟姉妹)など、相続人を調査します。実際に「面識のない甥姪が相続人になった」というケースも多く、相続手続きが複雑になることがあります。
甥や姪が相続人になる条件
故人(被相続人)に以下の条件を満たすと、甥や姪(被相続人の兄弟姉妹の子)も相続人となります。
- 被相続人に 子供や孫がいない
- 被相続人の 父母・祖父母もすでに亡くなっている
- 被相続人の 兄弟姉妹(甥姪の親)も亡くなっている(代襲相続)
法律上の相続権は、血縁関係と順位によって決まるため、日頃の親戚づきあいは関係ありません。上記の条件を満たし、代襲相続となる場合には、疎遠な、面識の無い甥や姪も相続人になることになります。相続財産が疎遠な甥や姪に行ってしまうこともあるのです(相続する甥や姪も迷惑かもしれませんが)。
兄弟姉妹、甥、姪には遺留分はない
しかし、兄弟姉妹、甥や姪には遺留分(法律で保障される最低限の取り分)がありません。これにより、遺言書を残すことによって、疎遠な、面識の無い甥や姪に相続させないように対策することができます。
※相続税対策などで甥や姪を養子にしている場合、その甥や姪は養子としての身分(子)であることから、第一順位の相続人になり、遺留分も認められます。
希望する相続人に財産を残すには遺言書の作成を
生前に遺言書を残すことで、希望する相続人に財産を渡すことが可能ですので、遺言書の作成を強くお勧めします。