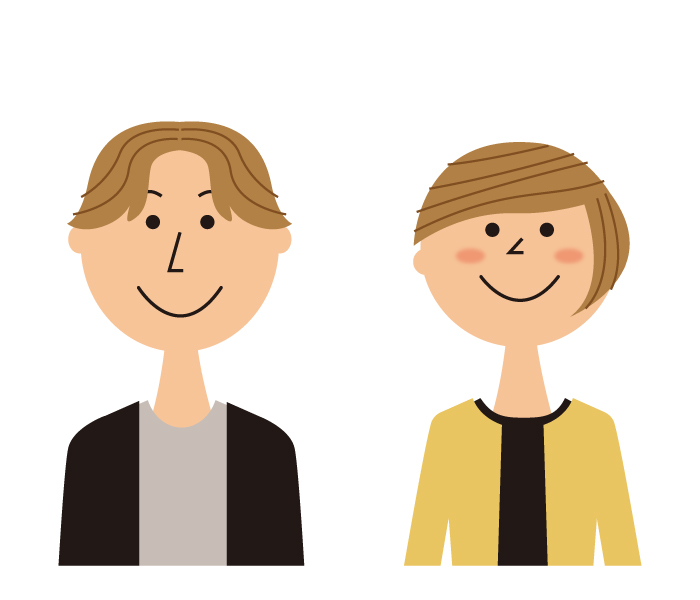みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
かつては、未成年者が結婚するには親の同意が必要でした。つまり、親の同意があれば、男性18歳、女性16歳の結婚年齢に達していれば未成年でも結婚できました。しかし、現在は未成年は結婚することができません。
成人年齢の引き下げ
2022年4月1日の民法改正において、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳は未成年ではなくなったわけです。
その理由としては、
- 世界的には成人年齢を18歳とする国が主流。
- 選挙権(公職選挙法)や国民投票権(憲法改正国民投票法)はすでに18歳以上に認められていた。
- 18歳、19歳の若者が自分の意思で契約や進路選択をできるようにすることで、社会参加を促進(親の同意なしに携帯契約、賃貸契約、クレジットカード作成などが可能になる)
- 18歳・19歳の若者が重大犯罪を犯した場合の扱いを見直す必要性。少年法も改正され「特定少年」として扱われるようになった。
婚姻年齢の改正
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられたのは、2022年(令和4年)4月1日です。これにより、女性も男性もともに結婚できる年齢が18歳以上ということになりました。
この改正の主な理由は、
- 男女間の法的な不平等を解消するため
- 国際的な人権基準(特に国連の女性差別撤廃委員会)への対応
- 社会的・経済的な成熟度を重視する現代の価値観に合わせるためなどです。
2022年4月1日以降の変化点
上記のような民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、同時に、婚姻年齢が男女ともに18歳に統一され、18歳以上であれば親の同意なしに婚姻可能となりました。
この改正によって、若者の自己決定権がより尊重されるようになったとも言えます。
日本では晩婚化が進んでおり、平均初婚年齢は男性で約31歳、女性で約30歳だそうです。若年結婚は少数派になりつつありますが、ライフスタイルの多様化により「早く結婚して早く自立したい」と考える人も一定数います。
結婚は愛だけでなく意思も必要
結婚するには、「愛」だけでは足りず、「意思」が必要です。結婚意思とは、社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思のことです。すなわち、結婚すると同居、協力扶助、相続といった法的効果を伴うことを理解して社会生活を夫婦としておくるという考えが必要です。通常、婚姻届けはこの結婚意思を表示するものとも考えられています。ですから、結婚するためには当人の合意とともに婚姻届けを提出する必要があるのです。
ちなみに、結婚意思がないのに婚姻届けを出す「偽装結婚」は法律上無効であり、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)という犯罪にもなります。