遺言は、自分の思いを残すためのものです。大切なひとのために、将来を考えてみませんか? 簡単にわかり易くご説明します
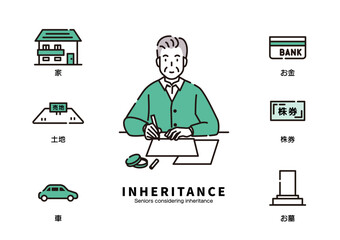
遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが「遺言書」です。15歳以上で意思能力(遺言の内容を理解し、その結果を弁識していること)がある場合は遺言をすることができるとされています。
遺言は法的な効力を持っており、遺言書があれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。そのため、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。
(注)但し、法定相続人のうちには「遺留分」という法律で定められた一定の相続人に保障される最低限の相続財産の割合があります。 この制度は被相続人の死後に相続人の生活を保障する目的で設けられており、この遺留分は遺言より法的に優先されますのであらかじめ注意が必要です。
また、遺言書のなかに、「付言事項」を書くこともあります。付言事項は遺言に追加できる記載事項のことで、法律上の効力は有しませんが、被相続人(亡くなった人)が家族などの相続人に対して感謝や希望などを記した手紙のようなもので、被相続人の気持ちを伝えるほか、揉め事を減らすためにも有効と思われます。
遺言書にも種類があります
遺言書の作成にもその方法によって大きく3つの方法、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。ご自身の状況、お考えによって選択してください。
自筆証書遺言(民法第968条)
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印をして作成する遺言書です。要件としては、自書であること(但し、添付する「財産目録」はパソコンや代書での作成が可能です。)、日付を確定すること(1月吉日という記載ではいけません)、押印があること(実印を推奨します。遺言書に印鑑証明を付することも有効です)が必要です。なお、また、保管は、遺言者によりますが、遺言者自身で保管する方法のほか、2020年7月10日施行の法務局「自筆証書遺言書保管制度」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)を利用し、法務局が保管することで遺言書の偽造や紛失を防ぐことができます。
公正証書遺言(民法第969条 第969条の2)
公正証書遺言は、証人2名の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成するものです。原則として公証人役場において作成することとなりますが、特別な事情がある場合には公証人に出張して対応していただくことも可能です。なお、公正証書遺言の作成には公証人に対する手数料がかかるほか、証人を2人立てることが必要です。証人が立てられないときは、公証人役場での紹介も可能です。公正証書遺言は公証人役場で保管されますので、偽造、紛失の可能性はありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成者 | 遺言者 | 遺言者が趣旨を口授し公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2人必要(家族や親族は承認になれません。公証役場で選任してもらうことも可能です。) |
| 作成費用 | かかりません | 公証人へ手数料がかかります。 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 (但し、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要。) | 不要 |
| 保管方法 | 遺言者が保管管理。但し、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管可能。 | 公証人役場で保管 |
| メリット | いつでも書ける。書き直しができる。 費用がかからない。 遺言内容を秘密にできる | 原本を公証役場で保管するので偽造や変造の危険がない。 公証人が作成するため無効になる可能性が低い。 家庭裁判所の検認が不要。 自筆できない場合も作成できる。 |
| デメリット | 紛失、変造、偽造の危険がある。 法定要件を満たさない場合や内容に不備があれば無効になる可能性がある。 裁判所の検認手続きが必要(法務局の保管制度を利用しない場合) | 利害関係のない証人が2名必要で、公証人と証人には遺言の内容が知られてしまう。 費用がかかる。 |
秘密証書遺言(民法第970条~第972条)
秘密証書遺言は、遺言書を作成したのち封印し、それを公証人が遺言者の遺言であること及び封印されていることを証明する遺言方式をいいます。この方法では、遺言の内容を遺言者以外には秘密にしておくことができます。この秘密証書遺言をする場合は、遺言者は遺言の全文、日付を記載し、署名、押印(実印をお勧めします)し、その印鑑をもって封印します。
なお、秘密証書遺言に不備があった場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしている場合は自筆証書遺言としての効力があります(民法第971条)。
遺言書の変更・撤回
一度作成した遺言書を変更することもできます。遺言を作成した後に、財産の変化があったり、財産の分け方を変えたりなど、その内容を変更したくなる場合があるかと思います。そもそも遺言は自由に作成、変更、撤回ができますので、ここでは遺言の変更についてそれぞれに見ていきましょう。
・変更の場合
作成した遺言の内容を変更したい場合、変更する部分が軽微で負担なく変更できる場合は、自筆証書遺言書であれば直接その遺言の文章を変更できます(民法968条3項)。方法は、変更したい部分を示し、変更した旨、変更内容を書き、署名し、かつその変更の場所に印を押すことになります。しかし、変更が多い場合や公正証書遺言の場合は、新たに遺言を作成するほうがよろしいでしょう。遺言は最も新しい日付の遺言が優先され、また、遺言が複数ある場合は、内容が抵触する部分は新しい遺言が優先されるため、新しい遺言を書けば前の遺言を変更できるのです(民法1023条)。
次に遺言の撤回ですが、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています(民法1022条)。
・自筆証書遺言の場合は、自分で書いた遺言を破棄してしまえばよろしいですね。
・公正証書遺言書の場合は、遺言書の「原本」が公証役場に保管されているので新たに撤回の遺言書を作成しすることになります。「遺言者は、●●地方法務局所属公証人〇〇作成の令和×年×月×日第〇〇〇号の公正証書遺言を全部撤回する。」という遺言書を作成することになります。なお、この場合の撤回遺言は、自筆証書遺言書でも公正証書遺言書でも可能です。
・公正証書遺言書の一部撤回については、撤回しない部分については、そのまま遺言の効力が残ったままとなります。したがって、撤回した新たな遺言と撤回前の遺言の2つが存在することになってしまいますので、実務上は全部撤回をしたうえで撤回のない部分も含めて遺言書を全て書き直す対応となります。
遺言を書いてみましょう
財産を調べる
不動産、現金、株券などの金融資産、高価な貴金属、クルマなど、自分の財産を調べてみてください。
・不動産 土地や建物などを登記簿、売買契約書などで特定します。
・現金や預貯金 どの銀行か、預金の種別、金額を口座ごとに洗い出します。
・金融資産 株券、債券、投資信託など、証券会社などの口座ごとに洗い出します。
・その他の財産 クルマや貴金属など
なお、財産目録は、パソコンでの作成も可能となりました。
だれに何を相続させるか、遺贈するかを決めましょう
妻に家と土地を、子供に現金をなど、具体的に誰にどの財産を相続してもらいたいか、また、家族以外の人や団体にも遺贈することもできますので、相続するひと、遺贈を受ける人の将来も考えて決めましょう。
遺言執行者を決めましょう
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために遺言通りに執行する権限をもつ人です。遺言執行者には「遺言の内容を実現するために、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限」があります。配偶者や子供など家族でも、行政書士などの専門家を選任することも可能です。
「相続させる」と記載する
「相続させる」と記載することには明確な法的メリットがあります。以下に詳しく解説します。
相続人に財産を渡す場合は「相続させる」がベスト
相続人に対して財産を渡す場合、「相続させる」と記載することで、相続登記を単独で申請できるようになります。
- これは、遺産分割の方法を指定したものとされ、遺言の効力が発生した時点で自動的に権利が移転するという扱いになります。
「遺贈する」との違い
| 表現 | 対象 | 法的扱い | 登記手続き |
|---|---|---|---|
| 相続させる | 相続人 | 相続による取得 | 単独申請可能 |
| 遺贈する | 相続人以外 | 贈与扱い | 遺言執行者または相続人全員の協力が必要 |
- 相続人以外に財産を渡す場合は「遺贈する」と記載する必要があります。「相続させる」と書くと無効になる可能性があります。
※最高裁の判断も「相続させる」文言を支持
- 最高裁判所は、「相続させる」旨の遺言は遺産分割の方法の指定であり、遺言者の死亡と同時に効力が生じると判断しています。
- ただし、相続人が遺言者より先に亡くなった場合は、その文言の効力が失われる可能性があるため、代襲相続の指定も記載しておくと安心です。
まとめ
相続人に財産を渡す →「〇〇に相続させる」、相続人以外に渡す →「〇〇に遺贈する」、代襲相続を想定する →「〇〇が死亡していた場合は△△に相続させる」と記載すると良いでしょう。
遺言の例
遺言の例は様々なものがインターネットに掲出されていますので、ぜひご参照ください。
遺言のご相談はぜひ当事務所へ
当事務所では、遺言をお考えの皆様のお手伝いをいたします。
遺言は法的要件を満たす必要があり、また、大切なひとへの大事なメッセージになります。当事務所では、皆様の思いをしっかりとお聞きしながら最適な遺言書の作成をお手伝いいたしますので、ぜひご相談ください。
ご相談のご連絡はお問い合わせフォームからよろしくお願いします。
お気軽にお問い合わせください。070-9044-9871受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください